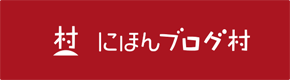私たちの周りには、テレビ、パソコン、スマートフォンなど、様々なディスプレイがあります。これらの画面の「アスペクト比(縦横比)」についての話です。少し長いですが、興味あればお付き合いください。
アスペクト比とは?
ディスプレイや映像の縦と横の長さの比率のことです。「ワイド(横長)」や「スクエア(正方形に近い)」といった言葉で表現されることもありますね。
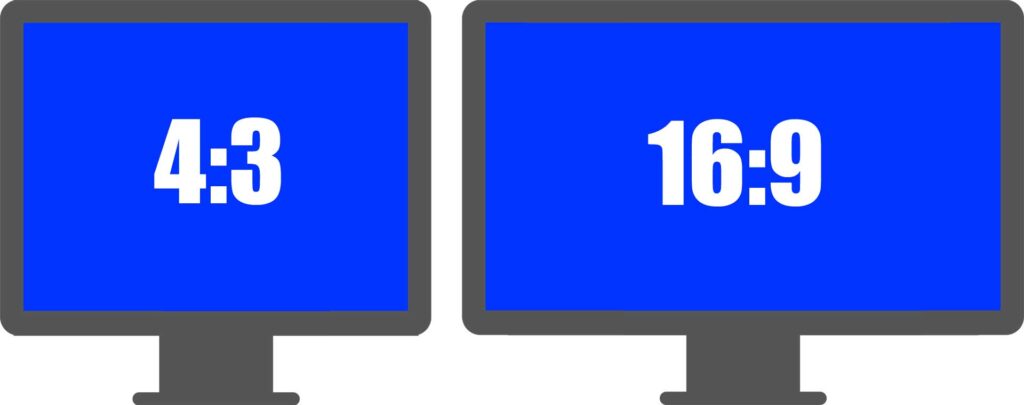
映画から始まった4:3
記録に残る最初の映像規格のアスペクト比は4:3でした。これは、発明王トーマス・エジソンの研究所にいたウィリアム・ケネディー・ディクソンが考案したとされています。なぜ4:3になったのか理由は不明とされていますが、この比率が初期の映画の標準となりました。
ちなみに、昔のコンピュータのディスプレイも主流は4:3でした。私もその時代のコンピュータで仕事をしていました。
テレビの登場と映画のワイド化
テレビが登場し、映画と同じ4:3のアスペクト比を採用しました。テレビが家庭に普及するにつれ、映画業界は観客を呼び込むための対抗策として、ワイドスクリーン化を進めます。これにより、シネマスコープサイズ(約2.35:1)など、様々なアスペクト比が乱立します。
その後16:9が採用された理由
その後、ハイビジョン放送(現在の地上デジタル放送など)が規格化される際に、新たな標準として16:9のアスペクト比が採用されました。この16:9という比率は、従来の4:3と2.35:1(シネマスコープサイズ)のほぼ中間で、どちらの映像ソースも比較的違和感なく表示できるということで決まりました。今のテレビで古い番組を観ると左右に黒帯が、ハリウッド映画などを観ると上下に黒帯が表示されますね。
今ではパソコンのディスプレイも16:9が主流となり、フルHDとも言います。最近では16:10のディスプレイも増えてきていますね。私自身、16:9と聞くと、すぐに1920×1080という数字が頭に浮かぶほど、基準として定着しています。4Kは3840×2160でフルHDを4倍したものです。
そして縦画面の時代
スマートフォンの登場により、「縦画面」が急速に普及しました。これは、スマートフォン本体の持ちやすさ、通話時に耳に当てるという電話の機能、そしてウェブサイトやSNSのタイムラインなど縦長のコンテンツとの相性が良いことなどが理由として考えられます。もちろん、スマートフォンを横向きにすれば、16:9などの横長動画も大きく表示されます。
スマホネイティブ世代は、テレビ番組をあまり観ないとも言われています。YouTubeのような動画は横長が基本ですが、ショート動画は縦長です。動画を縦で撮影する人も増えました。テレビ番組やニュースで、縦長のスマホ動画が紹介される際、画面の左右に大きな余白(黒帯)があり、中央に小さく表示されることがありますが、個人的には違和感があります。
日頃、パソコンの16:9の画面を見る時間が長い私にとって、縦長の動画はどうしても窮屈に感じてしまうのですが、スマホ世代にとっては縦長画面で動画を観ることが当たり前で、コンテンツも縦長が良いのだと思います。写真も縦の方が片手で撮りやすいという理由もあるかもしれません。

個人的な意見

全部16:9で統一すれば良いのに
私としては、コンテンツとデバイスが同じ比率であって欲しいので、全て16:9に統一してほしい。そうすれば画面に無駄な余白(黒帯)がなくて良い。写真を紙に印刷することが無くなったいま、写真を観るのは主にパソコンのディスプレイやスマートフォンになったため、ディスプレイに合わせて撮影したいのです。普段使っているコンデジ、ミラーレスカメラ、iPhoneも、写真の設定に16:9があるので、写真・動画ともに16:9にして、できるだけ横で撮影しています。写真を作品と捉えると、縦の方が印象的な場合もありますし、縦の方が向いている被写体もあるので、その場合は妥協して縦で撮ります。
最近のWordPressテーマも、ほとんどが16:9か16:10を意識して作られていますね。とくにアイキャッチ。
ちなみに、写真印刷で一般的なL判は約3:2、多くのミラーレスカメラやコンデジのイメージセンサーも3:2で、最大解像度で撮影すると3:2の画像になります。これを16:9で撮影・表示するということは、センサーの上下部分の画素を記録していないことになり、少し勿体ないとは感じます。
また、「ワイド化」と言いますが、視聴するデバイスが同じならワイドになるのではなく、実際には上下がカット(トリミング)されて狭くなっているだけだですね。
依頼を受けてスライドショーを作成することも多いのですが、プロジェクターでスクリーンに映したり、YouTubeにアップすることを前提にすると、16:9の横になります。ソースが縦だと、上下を大きくトリミングするか、上下にスクロールする手間が必要です。スクロールするのも、1枚あたりの表示時間が短いと速くて見にくいスクロールになります。スライドショーに使うことが前提の写真は、ぜひ横で撮影してください。
最後に「スマホ急性内斜視」など
人間の目は左右についているため、一般的には横長の視野の方が自然で、情報も捉えやすいと言われています。私自身も横長のディスプレイの方が見やすいと感じますし、スマートフォンのような小さい縦長の画面を長時間見ていると、目が内側に寄ってしまうような感覚になることがあります。
実際に「スマホ急性内斜視」といった症状も報告されており、特に子どもたちへの影響は気になるところです。
ディスプレイも多様性の時代なんでしょうね。コンテンツの種類や視聴スタイル、個人の好みによって最適なアスペクト比は異なるため、これからも様々な比率のディスプレイやコンテンツが登場し続けると思います。それぞれの特性を理解して上手に使いこなすことが必要だと思います。